
2025年9月19日、Appleは新型「iPhone 17」シリーズを発売した。
今年はラインナップ自体が刷新され、以前から噂されていた超薄型・軽量モデル「iPhone Air」がついに正式に登場。発表直後から大きな注目を集めている。
筆者はすでに「iPhone 17 Pro」を約1か月使用しており、その使用感については前回のレビューで触れたが、今回「iPhone Air」も約2週間ほど試用する機会を得た。結論としては、「Proを選んで正解だった」と感じる一方で、「Air」も非常に魅力的な一台であると実感する場面が多くあった。
本稿では、「iPhone Air」を実際に使用して見えてきた印象を中心にまとめる。すでに多くのレビュワーが取り上げているため、それ以上のことを伝えられるかは分からないが、この記事を通して何か新しい気づきを得ていただければ幸いだ。
iPhone Airを2週間使って見えた「良さ」

「iPhone Air」の最大の特徴は、その名の通り「薄さ」と「軽さ」にある。
本体の厚さは驚異の5.64mm。昨今のスマートフォンはバッテリーやカメラの大型化によって本体が厚くなる傾向にあったが、iPhone Airはそれを見事に覆した。
画面サイズは6.5インチとやや大きめながら、重量はわずか165gと最近のスマートフォンとしてはかなり軽い部類に入る。スーツやジーンズのポケットに入れても重さをほとんど感じない。
実際に手に取ると、薄く研ぎ澄まされたフォルムと、シャープな側面の仕上げが手にしっかりと馴染む。無駄をそぎ落としたデザインと優れた携帯性が、“軽快さ”と“洗練”を両立させている1台だと言えるだろう。



背面のバー状カメラについては賛否が分かれており、正直に言うと、筆者も「iPhone 17(無印)」のデザインのほうが好みではある。ただ、iPhone 17 Proほど主張が強すぎず、洗練されたシンプルさも感じられることから、むしろ “Airらしさ” をうまく体現していると言えるだろう。
カメラレンズの部分だけを出っ張らせるデザインにすれば良かったのでは、という意見もあるが、バー状の部分にはカメラだけでなくセンサー類も内蔵されており、各パーツの重心を分散させて安定性を確保するという意味では、合理的な構造とも言える。
ただし、この薄型・軽量化の実現のために機能面ではいくつかの「割り切り」が見られる。iPhone 17 Proと迷っている場合は、この部分をどう受け止めるかが選択の分かれ目になると言えるだろう。


「Pro」との明確な違い:カメラ性能とバッテリー駆動時間

iPhone AirとiPhone 17 Proとで大きく異なるのが、「カメラ」と「バッテリー」の2点。購入時にはこれらを重視するかどうかが選択の分かれ目になる。
Airは筐体の薄さを優先したため、背面には広角カメラのみが搭載されている。一方の17 Proは広角・超広角・望遠の3眼仕様で、撮影の表現の幅はiPhone 17 Proのほうが広い。旅行先で風景を撮ったり、イベントで遠くの被写体を狙ったりしたい場合には、iPhone 17 Proのカメラが有利だ。




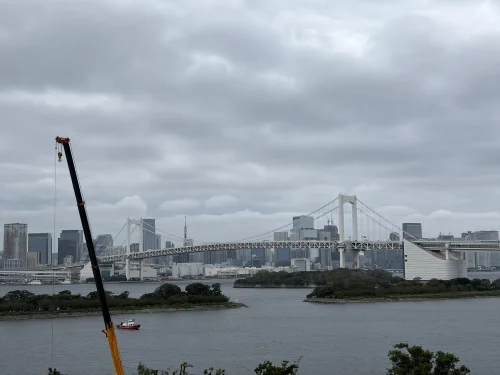

とはいえ、日常の撮影ではAirでも十分な仕上がりだ。試用中に撮影した風景写真では、広角カメラの画質はiPhone 17 Proとほぼ同等。望遠は非搭載だが、クロップによる2倍ズームや、28mm・35mm相当の中間ズームも使える。遠距離撮影を重視しないなら、大きな不満はないだろう。


バッテリー駆動時間に関しては、iPhone 17 Proの最大39時間(ビデオ再生)に対し、iPhone Airは27時間と控えめ。取材や出張で1日中外出するときにはやや心許なさを感じたが、デスクワーク中心であれば充電器を手元に設置するなどして、こまめに充電すれば問題ないだろう。
MagSafe対応のモバイルバッテリーや純正バッテリーパックを併用すれば、外出時でも手軽に電力を補える。筆者もかつてiPhone 12や13時代に純正バッテリーパックを利用していたが、移動の合間に1時間ほど充電するだけで十分な余裕ができた。軽快さを重視するなら、そうした運用も十分現実的だ。



このほかには、USB-Cポートの仕様とSoCのGPUコア数にも違いがある。
USB-Cポートは、AirはUSB 2.0(最大480Mbps)にとどまり、iPhone 17 ProのUSB 3.2 Gen 2(最大5Gbps)と比べると転送速度に大きな差がある。ミュージックアプリの同期などに時間がかかることは覚えておこう。
搭載されているSoCはiPhone 17 Proと同じA19 Proだが、iPhone AirはGPUコアが1基少なく、グラフィック性能もわずかに抑えられている。ただし、実際の使用において体感できるほどの差はほとんどないため、この点についてはあまり考慮しなくても良いだろう。
▼ Geekbench 6のベンチマークスコア比較
| 機種名 | 搭載SoC | CPUコア構成 | シングルコアスコア | マルチコアスコア |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro | A19 Pro | 高性能コアx2 高効率コアx4 | 3802 | 9678 |
| iPhone Air | A19 Pro | 高性能コアx2 高効率コアx4 | 3712 | 9699 |
| iPhone 16 Pro | A18 Pro | 高性能コアx2 高効率コアx4 | 3474 | 8567 |
| iPhone 16 | A18 | 高性能コアx2 高効率コアx4 | 3237 | 7775 |
| iPhone 15 Pro | A17 Pro | 高性能コアx2 高効率コアx4 | 2826 | 6840 |
| iPhone 15 | A16 Bionic | 高性能コアx2 高効率コアx4 | 2710 | 6512 |
| 機種名 | 搭載SoC | GPUコア構成 | Metalスコア |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro | A19 Pro | 6コア | 45647 |
| iPhone Air | A19 Pro | 5コア | 37421 |
| iPhone 16 Pro | A18 Pro | 6コア | 32671 |
| iPhone 16 Plus | A18 | 5コア | 28043 |
| iPhone 15 Pro | A17 Pro | 6コア | 28281 |
| iPhone 15 | A16 Bionic | 5コア | 22982 |
なぜ筆者は「Pro」を選んだのか

デザインだけを見れば、iPhone 17シリーズの中で最も完成度が高いのはAirだと思う。iPhone 17 Proについてはレビューで少し厳しい評価も書いたものの、それはAirのスマートな造形を意識していたためでもある。
発売から1か月ほど経ち、Apple Storeなどでユーザーの声を聞くと、「軽い」「持ちやすい」といった理由でAirを選ぶ人が意外に多い印象だ。数は少ないが電車や街を行き交う人のなかでも実際に使っている人を何度か目にした。スペックよりも使い心地の良さを優先する層にとって、Airは “ちょうどいいiPhone” になっているようだ。
それでも筆者が最終的にiPhone 17 Proを選んだのは、カメラ性能とバッテリー駆動時間の差によるところが大きい。
筆者は取材や出張の多い仕事柄、さまざまな画角で写真を撮影できることは必須条件だ。また、旅先で思いがけず美しい光景に出会ったとき、超広角や望遠があると表現の幅が広がる。
たとえば、イスタンブールのガラタ橋越しに見えるガラタ塔、香港のヴィクトリア・ハーバー、アリゾナのグランドキャニオン――そうした場所で、見たときの感動や思い出を写真にしっかりと収めるには、iPhone 17 Proのカメラ性能が必要だ。筆者と同じように“風景を綺麗に残したい”という人にとって、Proモデルを選ぶ理由は十分にある。

また、バッテリー駆動時間に関して、やはり取材や出張で1日中フル稼働しなければならないときには、iPhone 17 Proの長時間駆動が安心につながる。
モバイルバッテリーなどで途中で充電することもできるが、あれこれと色々なことを考えなければいけないときには、つい充電を忘れがち。いざ取材の現場に着いてからバッテリーが足りないと、重たいモバイルバッテリーをぶら下げた状態で使わなければいけなくなり、せっかくの軽さも台無しだ。
こうして色々な側面から分析してみると、Airでは満足できない層を自然にProへ導く差別化が、Appleの設計にはしっかり組み込まれていると感じた。
「Air」の思想が次世代iPhoneの方向性を示している可能性

「iPhone Air」は、現時点ではやや異端的な存在かもしれない。しかし、その設計思想には、今後のiPhoneシリーズに新しい風を吹き込むだけの力がある。初代モデルながら完成度は高く、数年先を見据えても十分に通用するポテンシャルを感じさせる仕上がりだ。
個人的には、現行のProモデルにもう少し軽快さが欲しいと思っている。必ずしもAirほど薄くする必要はないにせよ、軽さや取り回しの良さを重視する方向性は、これからのApple製品が進むべき道のひとつだろう。そうした意味でも、「Air」が提示したコンセプトは非常に意義深い。
今回筆者はカメラ性能やバッテリー駆動時間を優先してiPhone 17 Proを選んだが、それでも「Air」の存在には強く惹かれるものがある。競合であるサムスン電子の「Galaxy Z Fold7」が折りたたみ状態でも通常スマートフォン並みの薄さを実現しているように、将来的に登場が噂される折りたたみiPhoneにも、「Air」で培われたノウハウが生かされるかもしれない。
「Air」は単なる派生モデルではなく、“iPhoneの未来を先取りした1台”と言っていいのではないだろうか。数年後、この軽やかな思想がAppleの新しい標準となっていても不思議ではなさそうだ。




