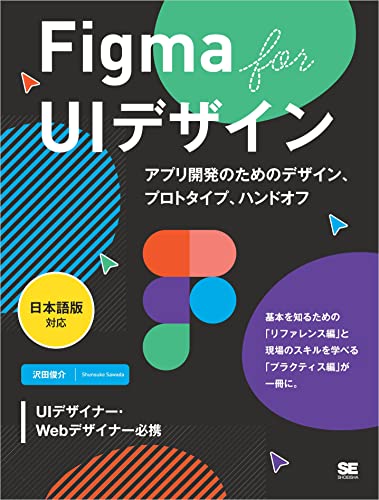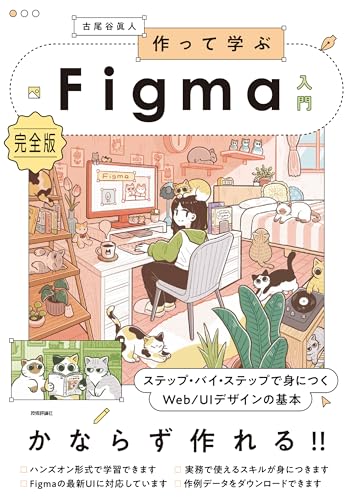米国発のデザインプラットフォーム「Figma」が日本で急成長している。2022年の日本法人設立から2年余りで、日経225企業の約半数で導入が進む。
その日本法人である「Figma Japan」を率いるのが、代表の川延浩彰氏だ。川延氏は前職で10年以上にわたり大手外資系IT企業でキャリアを積み、豊富な営業・マネジメント経験を持つ。
そして、ゼロから組織を立ち上げる経験を求めてFigmaに参画し、日本法人の設立から現在まで牽引してきた。Figmaのプロダクトが急速に浸透する背景には、ボトムアップ・トップダウン・パートナー戦略の3軸を掛け合わせた拡大戦略があると話す。
今回、川延氏に単独インタビューする機会をいただき、急成長するFigma Japanの日本市場における戦略や今後の展開についてお話を聞くことができた。本稿はそのインタビュー記事となる。
日経225企業の半数が導入。設立2年で急成長するFigma Japan、その成長を支える「3つの戦略軸」
筆者:
まず、Figma Japanが日本市場でどのように拡大を進めているか、そしてグローバルとの違いについてお聞きしたいと思います。ざっくり教えていただけますか?
川延浩彰氏:
Figma Japanの全体戦略は大きく分けて3つあります。まず一つ目として、もともと我々は「コミュニティレッドグロース」というビジネス戦略を採用しています。コミュニティの皆さんの力を借り、その熱量を大切にしながらボトムアップで成長していくというものです。
具体的にはさまざまな取り組みがあります。例えば、Figmaには「Friends of Figma」と呼ばれるグローバルなクリエイターコミュニティがあります。世界中に数百のコミュニティがあり、日本国内には地域ごとのコミュニティが北海道から沖縄まで20以上存在します。コミュニティ主催のイベントには、Figma Japan Educatorのように学校関係者が参加するなど、共通の関心を持つクリエイターに学びと協力の機会を提供するワーキンググループのような活動を通じて成長を後押ししています。
僕がFigma Japanに加わった2022年の時点では東京だけでしたが、その後徐々に数が増え、入社1年後の竹芝での1周年記念イベントを機に一気に広がりました。
もともと日本全国にFigmaを支えてくれるコミュニティの方々がいらっしゃるのは知っていましたが、単に知られていなかっただけではないかと思い、積極的に声をかけたことで広がりが加速したかたちです。
これをフェーズ1とすると、フェーズ2ではコミュニティ同士のつながりも強化されています。6月上旬には大阪で教育者向けの大型展示会「EDIX」が開催され、東京でも同様のイベントが行われました。東京では海外チームも参加しましたが、大阪ではリソースが限られていたため、コミュニティの皆さんやFriends of Figma大阪のメンバーが協力してくださり、大変助かりました。
2022年1月は社員が僕一人だけだったのですが、受付や呼び込みもコミュニティの方々が率先して手伝ってくださいました。その後、コミュニティ間のつながりはさらに強まり、有名な方は北海道や宮崎など遠方でも名前が知られるようになっています。
先日「IVS2025」で京都に行った際には、Friends of Figma宮崎の方と偶然お会いし、大阪のメンバーの名前を伝えたところ、すでに交流があることがわかりました。このようにネットワークが広がっていることを実感しており、今後もそのつながりを強化することで、ボトムアップの相乗効果がさらに高まると考えています。
次に人員体制についてですが、営業関連だけで、エンタープライズ、SMB、ミッドマーケット、戦略的セグメントに分けて担当しています。これらはトップダウン型の営業体制で、今後も投資を強化していく予定です。
また、5月後半にはパートナー戦略として、初のシグネチャーサービスパートナーであるゆめみさん (株式会社ゆめみ) と提携しました。これにより横の広がりを強化するとともに、日本独自の取り組みも進めつつ、グローバルの成功例を日本市場に合わせて展開していくことが効率的だと考えています。
筆者:
つまり、日本向けのプロダクトをゼロから作るのではなく、グローバルのプロダクトを日本市場にフィットさせていく形ということでしょうか?
川延氏:
はい。将来的に日本専用のプロダクトができる可能性はありますが、Figmaは世界中でスケールしているため柔軟性が大事です。ただ、インスパイアされている部分はあります。たとえば、FigJamの中の「washi tape」は日本の「マスキングテープ」が元ネタです。
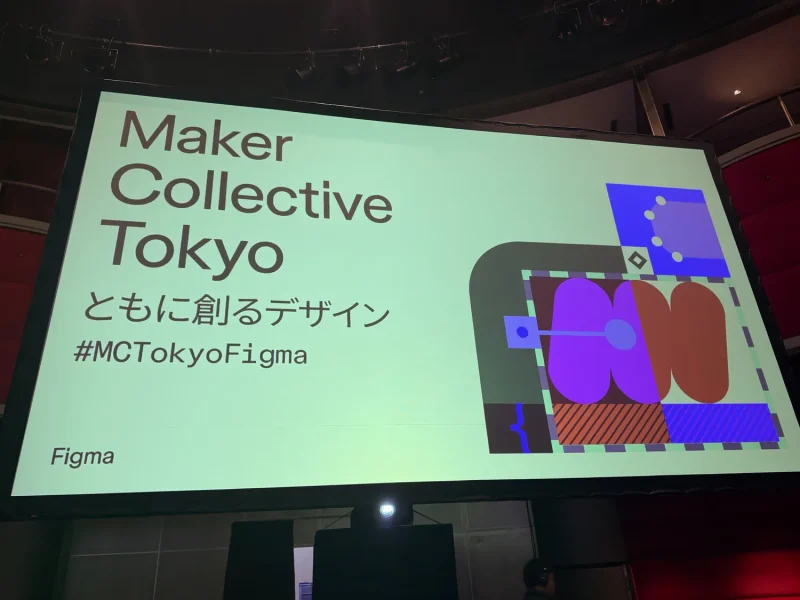
筆者:
Figmaが日本に本格進出する前までは、ユーザーの盛り上がりはそれほど大きくなかった印象ですが、実は日本上陸前から英語版を使っているユーザーも多かったですよね?
川延氏:
はい。イノベーターやアーリーアダプター層のネットネイティブ企業などが早期に使っていましたね。
筆者:
そのコミュニティの方々が、Figmaの日本への本格進出を知りワッと沸いたのが当時すごい印象的でした。6月のイベント (Maker Collective Tokyoのこと) も大盛況でしたし、熱意のあるコミュニティができているのは、こうしたコミュニティイベントが大きく影響しているのでしょうか。
川延氏:
イベントを開催するたびに喜んでいただけているのは確かです。今回のMaker Collective Tokyoも、SNS上で非常にポジティブな反応をいただいています。そういった反応があるということは、ポジティブに受け止めてもらえているのだと思います。
我々のイベントは単にコンテンツを流すだけでなく、必ずネットワーキングの時間を設けていて、そこで直接参加者の方々と話せる機会を大切にしています。
先日のイベントでも、会場の転換により一度外に出て再入場してもらう必要があり、本来なら離れてしまう方も多い状況でしたが、多くの方が残って参加してくださいました。皆さんがそうした交流の場を求めているのだと感じています。
筆者:
導入先としては、個人よりもエンタープライズが多いのでしょうか?
川延氏:
エンタープライズにも個々のユーザーがいるため比較できないのですが、2024年3月に開催したCEO来日時のプレスカンファレンスで、設立2年で日経225企業の約3分の1に導入されたと発表しました。現在では50%近くにまで増えており、この1年で大きく伸びています。
筆者:
半数近くに達しているのはすごいですね。導入が進む理由やきっかけは何でしょうか?
川延氏:
多くの企業がデジタルプロダクトを通じてエンドユーザーと接点を持っていることや、日本のパートナー企業の存在が大きいです。パートナー戦略も進めており、たとえばゆめみさんは「日本の企業をもっとインハウス化する」という考えを掲げていて、それは我々の方針にも合致しています。こうした中で自社のリソースで進めていこうという企業が増えてきており、徐々にその流れが来ていると感じます。
筆者:
目標としては、日経225全社への導入を目指しているイメージでしょうか?
川延氏:
日経225に属する企業は、多岐に渡るため、全社が日常的に弊社製品を使うのはなかなか難しいかもしれません。ただ、「なぜここで?」と驚くようなところでの導入もあり、新たな可能性を教えてもらっているとも言えます。
筆者:
意外な使われ方や導入事例はありますか?
川延氏:
意外というよりは、「やはりそうだよね」と感じたことがあります。例えば、僕たちは「Governance+」というセキュリティのアドオン機能をリリースしており、営業でも案内しています。
この「Governance+」は、より高度なセキュリティを提供するもので、日本では特に好評です。具体的には、近々重要なリリースを控えるIP(知的財産)を持つ企業が、情報漏えいリスクを防ぐためにセキュリティレベルを一段と引き上げたいと考えるのは自然な流れです。こうしたセキュリティ意識の高さは日本人に特に根付いていると感じており、今後さらに広がることを期待しています。
また、イベントでもご紹介した「Dev Mode MCPサーバー (※)」と呼ばれる新機能も日本で非常に好評です。7月にはDev Mode MCPサーバーをテーマにしたイベントを開催し、多くの方に参加いただきました。
※Dev ModeのMCPサーバーは、Model Context Protocolを用いてFigmaのデザイン情報(変数・コンポーネント・レイアウト等)をAIエージェントやIDEに接続し、選択フレームからのコード生成やCode Connectによる既存コンポーネントの再利用まで、デザインの文脈を保った実装を可能にする仕組み。
筆者:
導入企業の傾向として、どのような業種で導入が進んでいますか?また、逆にあまり導入が進んでいない業種はありますか?
川延氏:
基本的にバーティカルSaaSではないため、業種や業態はあまり選びません。
直近では日本で強い製造業や金融全般での導入が広がっている印象です。一方で、まだ開拓の余地があるのは、一見すると弊社から距離があるように見える分野です。そういったところは今も注視しています。何らかの形で浸透している傾向があり、まだまだ伸びしろは大きいと感じています。
Figmaの文化を日本に根付かせるローカルパートナーの力

筆者:
先ほどゆめみさんの話が出ましたので、その件について少しお聞かせください。そもそも、ゆめみさんとの提携はFigma Japanの代わりに他社への導入を促進するための第一歩という位置づけですよね?
川延氏:
弊社のパートナー形態は少しユニークです。ゆめみさんは弊社製品を直接販売するリセラーでもなく、ライセンスを流通させるディストリビューターでもありません。いわゆる「サービスパートナー」と呼んでいます。
たとえばワークショップの開催やマイグレーション支援、オンボーディング支援、さらに開発支援などに取り組んでいます。特に日本ではデザインシステムのニーズが高まっており、そうした案件を彼らが受注できることは双方にとってメリットがあります。
彼らは弊社製品をヘビーに活用し、Figma製品のスペシャリストとしてトレーニングも受けていますので、その前提でお仕事をお任せしています。
また、もし日経225企業のうち約半数がまだ弊社製品を導入していないとすれば、残りの企業群に対して、パートナーがすでに強固な関係性を築いていれば、弊社へ紹介してもらえる可能性があります。送客面での期待も大きく、加えて開発領域も含めて日本市場でより一層の力を入れていく必要があるため、そういった部分を補完してくれる強力なパートナーとの連携には大きな期待を寄せています。
筆者:
ゆめみさんがまず1社目のパートナーになりましたが、その他のパートナーについてはどうでしょうか?
川延氏:
もちろん話は進めています。ゆめみさんは「シグネチャーサービスパートナー」として発表していますが、独占契約ではありません。
筆者:
具体的な目標数は難しいかもしれませんが、どのくらいの規模感、社数を想定していますか?
川延氏:
現時点で明確な社数は定めていません。まずは1社目が軌道に乗り、ゆめみさんとの取り組みから学びを得つつ進めています。弊社の体制も整える必要があるため、バランスを見ながら慎重に進めている状況です。
また、数をむやみに増やすのではなく、パートナーとしてしっかり機能してもらえるかを見極めつつ、丁寧にコミュニケーションを重ねて着実に前進している段階です。
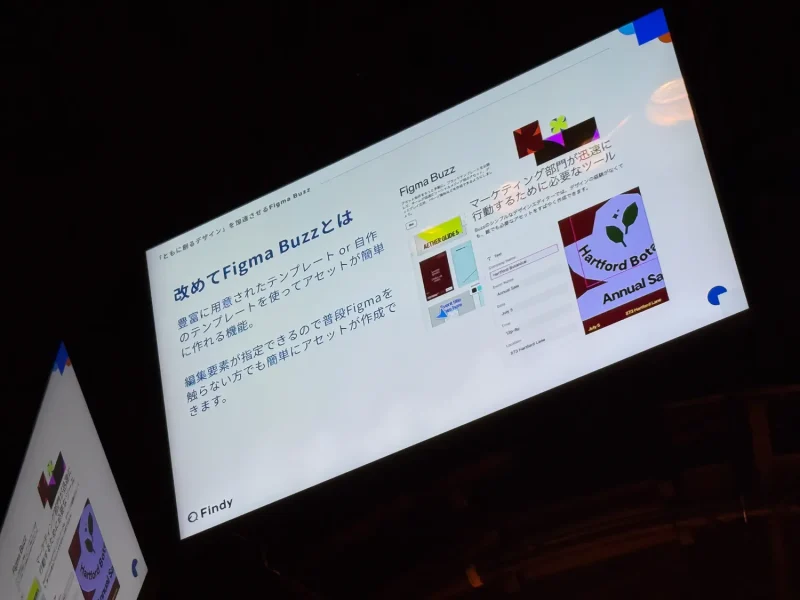
筆者:
Make/Sites/Draw/Buzzの各製品について、ユーザーからの現状の反応はいかがでしょうか?
川延氏:
僕の理解する範囲では、総じてポジティブな反応をいただいています。Figmaでカバーできる領域が広がっていることに対して様々なリアクションがありますが、全体としては良い反応だと感じています。
具体的には、Sitesのように弊社がホスティングまで行い、すぐにサイトが作れるサービスに対する期待は高いです。エンタープライズのお客様からも声をいただいています。
Drawについては、デザイナーの方から良い反応をもらっています。Makeは現在非常に注目されている領域で、外部コーディングなど関連分野でホットな状態で、間違いなく注目されている分野ではあります。
日本市場だけを「単独リージョン」として扱う意味とは
筆者:
Figma本社と世界各国の拠点網はどのように構築されているのでしょうか?
川延氏:
リージョン別で見ると、世界ではアメリカが本拠地になっています。アメリカ以外で最初に拠点を置いたのはロンドンで、2020年に設立されました。日本は2022年7月に設立されました。現在、ヨーロッパにはパリとベルリンにも拠点があり、ヨーロッパ全域に加えてアフリカ大陸や中東地域もカバーしています。
さらに、日本国外では2023年5月にシンガポールに拠点を置き、アジア・パシフィック地域での事業拡大を進めています。シンガポール拠点はニュージーランドからインドまでをカバーしており、かなり広範囲です。オーストラリアにもオフィスを設置しており、今後さらにアジア・パシフィック地域の拡大が見込まれています。
先日、ブラジルでローンチパーティーを開催し、南米地域はこれから本格的に展開していく段階です。
筆者:
拠点作りの方針は、Figma本社の意向に基づいたものなのでしょうか?
川延氏:
はい、その通りです。拠点はリージョナルヘッドクォーターのイメージで設置されています。ロンドン、日本、シンガポールがリージョナル拠点として機能しています。
ロンドンを設置した際に、広い範囲をすべてカバーするのは難しいため、パリとベルリンにも拠点を置きました。同様にシンガポール拠点から全域をカバーするのも難しい部分があり、オーストラリアはシドニーに独自の拠点を設けたかたちです。
日本だけは唯一、単独の拠点 (Single Country, Single Region) で運営されています。
筆者:
グローバルの視点で見たとき、Figmaの日本市場の位置づけを教えてください。利用者はやはりアメリカが多いのでしょうか?
川延氏:
国別の利用者数はまだ公開していないため具体的にはお伝えしづらいのですが、海外のユーザーが圧倒的に多いのは公表しています。
ちなみに、米国外での利用者は約85%という割合。近いところで言うと、近隣の韓国でもかなり使われています。
筆者:
日本だけ単独の拠点にする理由は何かあるのでしょうか?
川延氏:
日本市場の重要性を会社として十分に理解していることが大きいと思います。加えて、日本市場の特有の事情も理解してくれています。
だいたいこういった形で外資系のオペレーションを回していらっしゃるところって、日本はAPAC (アジアパシフィック) の一部としてまとめられることも多いんですけど、Figmaの場合は日本は単独なんです。
筆者:
Figma本社から見て日本市場への期待感は高い?
川延氏:
僕が入社してから3年半、ずっと日本単独の報告を続けていますし、そういう意味で引き続き大きな期待をかけられているのだと思います。これが一番わかりやすいポイントではないでしょうか。
川延氏がFigma Japanに関わったキッカケと、設立から2年

筆者:
川延さんがFigma Japanに携わろうと思ったキッカケは何だったのでしょうか?
川延氏:
僕は外資系企業の中でも珍しく、前職には10年以上在籍していました。そこで10年以上いろいろな経験をさせてもらいました。しかし、10年経った時点で「このまま続けるべきかどうか」という判断を迫られた時に、Figmaの話があり、選択肢は前職に残るかFigmaに行くかの二択でした。
Figmaではゼロから立ち上げるという難しさとやりがいがあり、大学院でも学び、私がすごく興味があるアントレプレナーシップの観点からも素晴らしい機会だと感じました。自分が直接何かを作るわけではありませんが、市場や事業を創るという意味では、アントレプレナーシップの精神に通じるものがあります。前職ではゼロから立ち上げる経験はなかったので、その挑戦をさせてもらえるのは非常にありがたい機会でした。
筆者:
そこから3年半が経ちましたが、いかがですか?
川延氏:
決してスムーズな道のりではなく、やりながら学んでいくことも多かったです。会社自体も大きく変わってきましたね。僕が入社したときは社員が約500人でしたが、今は約1,600人に増えています。製品も当時は2つしかありませんでしたが、現在は8つに拡大しました。非常に速いスピードで多くの変化が起こっている環境に身を置いていると感じます。いわゆる「ドッグイヤー (IT業界の技術進化の速さを犬の成長に例えた言葉)」を強く実感していますね。
筆者:
本当にスピード感がすごいですよね。導入率が日経225社中50%というのも驚異的です。
川延氏:
そうなんですよね。でも、まだまだ成長の余地があると思っています。周囲には非常に優秀な人たちが多く、日々学びも多いですし、彼らの発想には驚かされることも多いです。いろんな意味で成長させてもらえる環境だと感じています。
筆者:
もしよろしければ、日本リージョンをマネジメントする上での苦労話などがあれば教えてください。
川延氏:
一般論になってしまうかもしれませんが、関わるステークホルダーが非常に多く、時差や言語、文化的背景も全く異なる中で、同じ説明でも理解される人とそうでない人がいます。その感覚を掴むことが重要で、僕の立場だとどうやってそれを調整していくかが求められます。どの人にはこう話せば伝わる、こう話したいのだということをいち早く読み解く能力が必要です。
また、ディベート力もこの会社ではより一層求められていると感じています。例えば日本人は教育過程で先生の言うことを聞き、Qに対してAを出す訓練を受けてきます。それは知識を積み上げる点で有効ですが、応用力があまり養われない面もあります。
一方で海外の方は応用力が高く、ダイナミックにトピックが動く中でも批判を恐れず自分の意見をしっかり通す姿を日々目にします。そうした力はこれからの時代、より一層必要になると思います。日本国内だけで仕事をするなら問題ありませんが、世界と仕事をするなら、自分の意見を論理的に説明し、ディスカッションやディベートを行う力が不可欠だと痛感しています。
筆者:
バックグラウンドの異なる方が多いということですね。
川延氏:
そうですね。例えば僕が参加する会議では、英語が堪能なドイツ人、フランス人、イギリス人、アメリカ人など多様な国籍の方がいます。アメリカ人の中でも様々なバックグラウンドを持っている方がいます。共通言語は英語ですが、彼らは母国語として英語を話す人もいれば、そうでない人もいます。そういった多様な相手とコミュニケーションを取ることは、日本が国際社会で生き残っていく上で重要な課題だと思います。
僕は「カルチャーマップ」というエリン・メイヤー氏の著書をよく紹介するのですが、日本は文化的にアメリカと対極的な立ち位置にあります。アメリカが左側なら日本は右側にいる、というように文化の違いを非常に考えさせられます。
ディスカッションの場でも日本人は空気を読んで「自分が言わなくても誰かが言うだろう」とか、「これを言うと馬鹿だと思われるかもしれないから控えよう」と考えがちですが、海外の方はそうではありません。上司であっても真っ向から意見を言うケースも多いです。そこは大きな違いだと思います。
筆者:
日本市場への展開はどのような段階を経て進めてきたのですか?また、その中で特に重視したポイントは何でしょうか。
川延氏:
大きく3つのフェーズがあって、最初は本格的なローカライゼーションの時期でした。日本にオフィスを置く決断もその一環です。日本市場に向き合う上で、ローカライズは必須だと考えました。その後、何をローカライズするか、優先順位をどう付けるかといった課題も出てきました。サポートページは膨大な数があり、全部対応するのは難しいため、取捨選択が必要です。
また、日本ではX (旧:Twitter) の利用がとても多いため、スタンドアロンで公式アカウントを設ける必要がありました。こうした大きな方針決定の後に、具体的なやり方が決まっていくという流れです。
Figmaの日本展開のローンチのタイミングは丁寧に準備しました。教育分野も同じ流れで進めています。パートナーシップについても、まずは市場とパートナー双方にとって最適な形を模索しています。今後も変化や新しい展開が続くと思いますが、今回の取り組みはその第一歩と考えていただければと思います。
筆者:
日本のパートナーやユーザーと取り組む際に意識している工夫や、日本市場ならではのアプローチはありますか?
川延氏:
僕が求めて実現したこともあれば、そうでないものもあります。たとえば教育分野では、情熱を持った方がサイドプロジェクトとして始め、それが軌道に乗った結果、現在は専任で取り組んでいただいている事例があります。そうしたケースもありますが、共通して大事にしているのは「まずやってみる(Run With It)」という姿勢です。
つまり、必要だと感じたらまず動いてみる。リソースが限られていても工夫しながら前に進み、実績を積み重ねてから広げていく。大企業的に準備を整えてから動くのではなく、スタートアップらしくスピード感をもってチャレンジする。そのスタイルが日本でもしっかりフィットしていると感じています。

筆者:
現在のデザインツール市場の動向について、御社として特に注目している点はどのようなところでしょうか?
川延氏:
僕たちは競合他社を見るというよりも、ユーザーの皆さんに徹底的に向き合うことが正しいアプローチだと考えています。先ほどのイベントもその一例ですが、こうした機会を大切にしていきたいと思っています。実際に使っている方、まだ使っていない方から直接リアクションをいただくことは非常に重要ですし、僕自身も積極的に意見を聞いていく必要があります。ユーザーに真摯に向き合いながら事業を展開していくことが何より大切だと考えています。
筆者:
最後に、読者の皆さんへ伝えたいことがあればお願いします。
川延氏:
改めて強調したいのは、日本のマーケットが非常に重要であるということです。これまでできていなかったことも、これから積極的に取り組んでいかなければならないと考えています。特に、単独での展開が難しかったパートナー企業との連携も、その一例として挙げられます。教育事業も着実に広がっており、今後の展開にぜひご期待いただきたいと思います。
また、皆さんからのさまざまなご意見を真摯に受け止めたいと考えていますので、製品をご利用いただいた際には、ぜひフィードバックをお寄せいただければ幸いです。
筆者:
ありがとうございました!